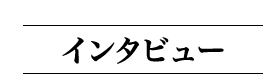松山ケンイチ
 ―母と息子の話でもあり、兄と弟の話でもあり、社会的なテーマもある作品ですが、
―母と息子の話でもあり、兄と弟の話でもあり、社会的なテーマもある作品ですが、
完成した作品をご覧になっていかがでしたか?
原発事故から3年近く経ってこのような作品が生まれたことは、あの時から前に進んでいるということです。今現在も手つかずの場所があったり、生活環境があの時と変わらない人々がいても時間は経ち、メディアが次から次へと新しい話題を提供している中で、新しくこの作品が生まれたことがとても大事だと思います。
―沢田次郎という役どころをどのように捉えて演じられましたか?
リセット族という人々の話を聞いて、なんとなく次郎の気持ちが分かるような気がしました。田圃や土など自然と同化していくようなキャラクターなので、どこにも棘がないように演じました。
―久保田直監督とのお仕事はいかがでしたか?
監督と話していると人間の新鮮なところを話してくださったりして、良い意味で演技に取り入れることが出来ました。映画の撮影現場も自分のフィールドにしていただいて、またご一緒できたらと思います。
―内野聖陽さんはじめ、田中裕子さん、安藤サクラさんとの初共演はいかがでしたか?
とんでもないキャストの方々だなと思いました。監督はどうやってまとめるんだろうと思っていましたが、みなさんのそこに生きている感覚が物凄いです。説得力があります。素晴らしいです。
―撮影中の印象に残ったエピソードを教えてください。
農業指導の秋元さんとの出会いですね。土や田圃にこれでもかというくらい愛情を与えている。何かに愛情を与えている人は、人間にもとても優しい。「孫の口に入るものを作ってるんだから、土から愛情持ってやらないと」という言葉に感銘を受けました。人様の目に、耳に入る映画ですから僕もたっっっぷり愛情を持ってやらせていただきました。
内野聖陽
 ―母と息子の話でもあり、兄と弟の話でもあり、社会的なテーマもある作品ですが、
―母と息子の話でもあり、兄と弟の話でもあり、社会的なテーマもある作品ですが、
完成した作品をご覧になっていかがでしたか?
ごく単純な「再生」という人間の営みが、そこで途切れて、できなくなってしまうことの恐ろしさを感じました。
―沢田総一という役どころをどのように捉えて演じられましたか?
福島の悲しみは、簡単には理解できないし、してはいけないけれど、総一の持っている閉塞感を表現するには、彼の地で、すべてを奪われた人の悔しさ、悲しさ、怒り、無念さ、そういうものを肌で感じなければいけないと思い、常に、現地の方と触れ合うようにしました。
答えの出ない中で、実際に生活されている方のことを思うと、今でも演じ切れたのか懐疑的になります。
――久保田直監督とのお仕事はいかがでしたか?
常に、嘘の時間・空間を排除した演出で、最後まで、俳優の持つ真実を期待し、信じてくださっていたように思います。ドキュメンタリーという、フィクションの中にはない視点でシーンを作り上げようとしていたので、いろいろ勉強させていただきました。
―初共演の松山ケンイチさんはじめ、田中裕子さん、安藤サクラさんとの共演はいかがでしたか?
裕子さん以外は、初面識でしたが、本当に暖かい福島の方々との触れ合いの中で、いつの間にか自然と「家族」という繋がりを空気として醸し出せていたのが不思議でした。
―撮影中の印象に残ったエピソードを教えてください。
田植えのシーンでは、地元の皆様が、長い待ち時間にもかかわらず、嫌な顔一つせず、率先して手伝ってくださったこと。土地を愛し、米作りに誇りを持つ農業家の方たちの姿に、嬉しさがこみ上げ感動しました。
―この作品に込めた思いを教えてください。
僕が演じた総一という男は、『希望』というエネルギーをむしり取られた男です。それでも、なんとか明日があって欲しいという、祈りにも似た気持ちで参加させていただきました。
監督:久保田直
―『家路』を制作しようと思ったきっかけを教えてください。
震災後に今回企画協力で入っている是枝裕和さんを含めた仲間と「正義感じゃないけど、何かやりたい」という話になったり、脚本の青木研次さんと飲んでいた時に「福島と震災は全く別だよな」という話になったりしたんです。福島ではある日いきなりそこに“閉鎖された空間”というものができた。目の前にある自分の故郷に入れないってどういうことなんだろう?と。そこで思ったのが、誰もいなくなったからこそ、そこに帰るっていうことってあるんじゃないかということでした。もともと、ドキュメンタリーの仕事で家族をテーマにすることが多かったこともあり、福島の農家の家族というテーマを決め、現地で色々な取材をして被災者の方々の経験などを青木さんがうまく脚本にしてくれました。
―ドキュメンタリー出身ということでこだわりはありましたか?
物事や人をどう見るか、というのが演出だと思うんですが、そういう目はドキュメンタリーの仕事でだいぶ養われたと思います。以前、ゲイの10代の少年が妹にカミングアウトする瞬間を撮るという番組を制作した時に、こちらとしては眉間にしわを寄せながら話すんだろうなと予測していたんですが、実際は全然違ったんです。笑うんですよね、にたぁっと。「いや、実はさ…」と話して、ずっと笑っているんです。
もし自分がそういうのを知らずに、そういうシナリオがあって、告白する、というト書きがあった場合、役者さんに「笑いましょう」とは絶対言わないと思います。でもよく考えると、大事な時とか追い詰められた時に、人って意外と笑ったりするなというのはありました。そういう経験が、今回の『家路』で学校の教室で松山さんが手をあげるシーンをはじめとする演出につながったと思います。あの演技はゾクゾクっとしました。いい役者だなと思いました。
―この作品に込めた思いを教えてください。
「家族ってなんだろう」というのが、今までの自分の仕事の大きなテーマとしてありました。たくさんの家族を取材するうちに、「生きていること」、「人間であること」というのは普遍的で、世界共通なんだなということを感じてきました。震災後を描いた作品ではありますが、それだけではない。それを感じてもらえればと思います。